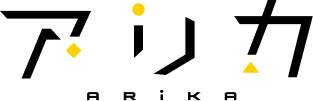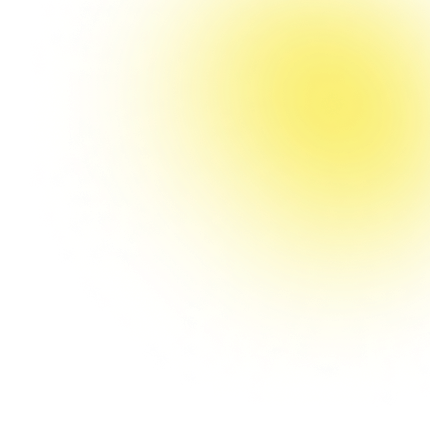Blog
ブログ
2025.11.06
SEO
SEO対策における画像最適化の完全ガイド|効果的な実践方法を解説!
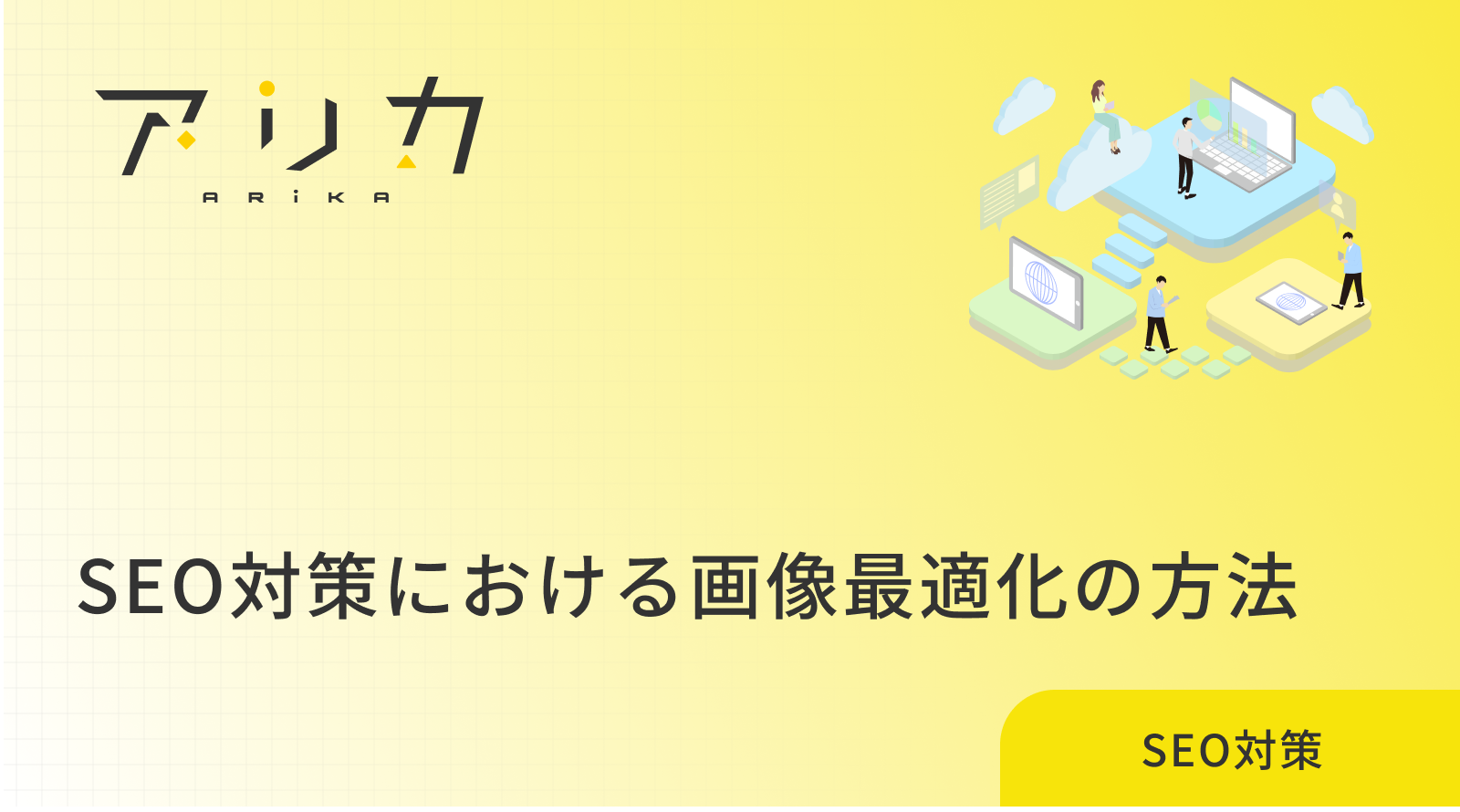
「記事に画像をたくさん使っているのに、ページの表示速度が遅い」
「画像検索からの流入がほとんどない」
「PageSpeed Insightsのスコアが改善しない」
このような悩みを抱えているWebサイト運営者やSEO担当者の方は少なくありません。
実際、画像の扱い方一つで、サイトのパフォーマンスや検索順位に大きな影響が出るケースは非常に多く見られます。
しかし、適切な画像最適化を行うことで、ユーザー体験が向上し、SEO効果も飛躍的に高まるでしょう。
本記事では、SEO対策における画像最適化の重要性から、具体的な実践方法、よくある失敗パターンまで、すぐに活用できる内容を分かりやすく解説します。
SEO対策で画像最適化が必要な4つの理由

まずは、なぜSEO対策において画像最適化が重要なのか、主な理由を把握しましょう。
見出しのポイント
- ❶ ユーザーの離脱率を下げられる
- ❷ 画像検索経由の流入が見込める
- ❸ Google Discoverに掲載されやすくなる
- ❹ SEO経由の流入を増やせる
画像最適化がもたらす効果を理解することで、取り組むべき優先度が明確になります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
ユーザーの離脱率を下げられる
ページの読み込み速度は、ユーザー体験に直結する重要な要素です。
画像が最適化されていないと、ファイルサイズが大きくなり、表示に時間がかかってしまいます。特にモバイル環境では、数秒の遅延でもユーザーは離脱してしまうかもしれません。
Googleの調査によると、ページの読み込み時間が1秒から3秒に増えると、直帰率は32%上昇するというデータもあります。
参照:Find out how you stack up to new industry benchmarks for mobile page speed
適切な画像最適化によって表示速度が改善されれば、ユーザーが最後まで記事を読む確率が高まり、結果的にコンバージョン率の向上にもつながるでしょう。
画像検索経由の流入が見込める
Google画像検索は、多くのユーザーが利用する重要な検索チャネルです。
適切なalt属性やファイル名を設定することで、画像検索結果に表示される機会が増え、そこから自社サイトへの流入が期待できます。
特に商品画像や図解、インフォグラフィックなど視覚的な情報を求めるユーザーにとって、画像検索は主要な情報収集手段となっています。
画像最適化を行うことで、テキスト検索だけでなく画像検索からも安定したトラフィックを獲得できるようになります。
Google Discoverに掲載されやすくなる
Google Discoverは、ユーザーの関心に基づいてコンテンツを自動的に表示する機能です。
Discoverに掲載されるためには、高品質な画像が不可欠とされています。
Google公式ガイドラインでは、幅1200ピクセル以上の大きな画像を使用することが推奨されており、適切に最適化された魅力的な画像があることで、Discoverへの掲載確率が高まります。
Discoverからの流入は、能動的に検索していないユーザーにもリーチできるため、新たな読者層の獲得につながる重要なチャネルと言えます。
SEO経由の流入を増やせる
画像最適化は、総合的なSEO評価の向上に寄与します。
Googleは「Core Web Vitals」という指標でページのユーザー体験を評価しており、その中でも画像の読み込み速度は重要な要素です。
特にLCP(Largest Contentful Paint:最大コンテンツの描画時間)は、ページ内で最も大きな要素が表示されるまでの時間を測定する指標で、多くの場合、画像がこの対象となります。
画像を適切に最適化することでCore Web Vitalsのスコアが改善され、検索順位の向上につながる可能性があります。
結果として、オーガニック検索経由での流入増加が期待できるでしょう。
画像最適化でチェックすべき5つの基本項目

次に、画像最適化を行う際に必ず確認すべき基本項目を見ていきましょう。
基本項目は以下のとおりです。
基本項目
- ❶ ファイル形式の選び方
- ❷ 適正なファイルサイズ
- ❸ 画像サイズ
- ❹ ファイル名
- ❺ alt属性
各項目の特徴を理解し、自社サイトの画像を適切に最適化することが重要です。それぞれ詳しく解説します。
ファイル形式の選び方(JPEG・PNG・WebP)
画像のファイル形式は、用途に応じて適切に選択する必要があります。
代表的なファイル形式として、JPEG、PNG、WebPがあり、それぞれに特徴があります。
| 形式 | 特徴 | 適した用途 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| JPEG | 写真など色数の多い画像に適している | 商品写真、人物写真、風景写真 | 小〜中 |
| PNG | 透過処理が可能、ロゴやアイコンに最適 | ロゴ、アイコン、透過が必要な画像 | 中〜大 |
| WebP | JPEGより25〜35%軽量、透過にも対応 | すべての用途に推奨される次世代形式 | 最小 |
現在、WebPは主要なブラウザでサポートされており、画質を保ちながらファイルサイズを大幅に削減できるため、積極的に採用するのがおすすめです。
ただし、古いブラウザへの対応が必要な場合は、JPEGやPNGをフォールバック用に用意しておくとよいでしょう。
適正なファイルサイズ
画像のファイルサイズは、ページ全体の読み込み速度に直接影響します。
一般的に、1枚あたりの画像ファイルサイズは100KB以下を目標とし、最大でも200KBまでに抑えることが理想的です。
アイキャッチなど大きく表示する必要がある画像でも、300KB以内に収めるよう心がけましょう。
ファイルサイズが大きすぎる場合は、圧縮率を調整するか、画像サイズ自体を見直す必要があります。
複数の画像を掲載するページでは、ページ全体の画像合計サイズも意識し、モバイル環境でも快適に閲覧できるよう配慮することが大切です。
画像サイズ(縦横ピクセル)
表示サイズに対して不必要に大きな画像を使用すると、ファイルサイズが増大し、読み込み時間が長くなります。
コンテンツ幅が800ピクセルのサイトで、3000ピクセル幅の画像を使用しても、余分なデータ量を転送するだけで意味がありません。
実際に表示される最大サイズの1.5〜2倍程度の解像度で用意し、レスポンシブ対応のために複数サイズを準備することが推奨されます。
具体的には、以下のような画像サイズが目安となります。
| 用途 | 推奨サイズ | 補足 |
|---|---|---|
| ブログ記事内の画像 | 幅800〜1200px | コンテンツエリアの幅に合わせる |
| アイキャッチ画像 | 幅1200〜1600px | SNSシェア時の表示も考慮 |
| サムネイル画像 | 幅300〜500px | 一覧表示用の小さいサイズ |
| 全幅表示の画像 | 幅1920〜2400px | 高解像度ディスプレイにも対応 |
HTMLのsrcset属性を使用すれば、デバイスの画面サイズに応じて最適な画像を配信でき、モバイルユーザーの通信量削減にもつながります。
ファイル名
画像のファイル名は、検索エンジンが画像の内容を理解するための重要な手がかりです。
「IMG_1234.jpg」のような意味のない名前ではなく、画像の内容を説明する具体的な名前を付けましょう。
例えば、SEO対策に関する記事の図解であれば「seo-taisaku-gazo-saitekika.jpg」のように、キーワードを含めた分かりやすい名前にします。
ファイル名を付ける際のポイントは以下のとおりです。
ファイルの名をつける際のポイント
- ❶ 日本語ではなく英数字とハイフンを使用する
- ❷ 単語の区切りはアンダースコアではなくハイフンを使う
- ❸ 関連キーワードを自然に含める
- ❹ 具体的で説明的な名前にする
- ❺ 長すぎない名前にする(目安は3〜5語程度)
適切なファイル名を付けることで、画像検索での表示機会が増え、SEO効果の向上が期待できます。
alt属性(代替テキスト)
alt属性は、画像が表示されない場合や視覚障害のあるユーザーがスクリーンリーダーを使用する際に、画像の内容を伝えるためのテキストです。
SEOの観点からも、検索エンジンが画像の内容を理解するための重要な情報源となります。
alt属性を設定する際は、画像の内容を正確に説明し、自然な形でキーワードを含めることが大切です。ただし、キーワードの過度な詰め込みは逆効果となるため注意が必要です。
良いalt属性の例として、SEO対策の図解であれば「SEO対策における画像最適化の5つのチェック項目を示した図」のように、画像が何を表しているかを具体的に説明します。
一方、「SEO 画像 最適化 対策 方法」のようなキーワードの羅列は避けましょう。
装飾的な画像や意味を持たない画像には、空のalt属性(alt="")を設定することで、スクリーンリーダーがその画像を読み飛ばすようになり、アクセシビリティが向上します。
今すぐできる画像の軽量化テクニック3選

画像最適化の基本を理解したら、次は実際に画像を軽量化する具体的なテクニックを見ていきましょう。
軽量化テクニックは以下のとおりです。
軽量化テクニック
- ❶ 無料ツールで80%圧縮する方法
- ❷ WebPへの変換方法
- ❸ 遅延読み込みの実装方法
これらの手法を組み合わせることで、大幅なパフォーマンス改善が期待できます。それぞれ詳しく解説します。
無料ツールで80%圧縮する方法(TinyPNG・Squoosh)
画像の軽量化には、専門知識がなくても使える無料ツールが数多く存在します。
代表的なツールとして、TinyPNGとSquooshがあります。
TinyPNGは、PNGとJPEG画像を視覚的な品質を保ちながら圧縮できるWebサービスです。
一度に最大20枚、各5MBまでの画像を処理でき、平均で50〜80%のファイルサイズ削減が可能です。
Squooshは、Googleが提供する画像圧縮ツールで、ブラウザ上で動作し、圧縮前後の画像を並べて比較しながら最適な設定を見つけられます。
WebP形式への変換にも対応しており、細かい圧縮設定が可能です。
これらのツールを使用する際は、圧縮後の画像を必ず目視で確認し、品質が許容範囲内であることを確認してから使用しましょう。
特に商品画像やロゴなど、細部が重要な画像では過度な圧縮を避ける必要があります。
WebPへの変換方法
WebP形式は、同等の画質でJPEGやPNGよりも大幅に軽量なファイルを作成できる次世代の画像フォーマットです。
WebPへの変換方法は複数ありますが、最も手軽なのはSquooshやCloudConvertなどのオンラインツールを使用する方法です。
既存の画像をアップロードし、出力形式としてWebPを選択するだけで変換できます。
WordPressを使用している場合は、EWWW Image OptimizerやShortPixelなどのプラグインを導入することで、アップロード時に自動的にWebP形式に変換できます。
これらのプラグインは、WebPをサポートしていないブラウザに対して自動的に元の形式の画像を配信する機能も備えています。
HTMLで直接WebPを使用する場合は、<picture>要素を使って以下のように記述することで、ブラウザのサポート状況に応じて最適な形式を配信できます。
<picture>
<source srcset="image.webp" type="image/webp">
<img src="image.jpg" alt="説明文">
</picture>
この方法により、WebPをサポートするブラウザでは軽量なWebP画像が、サポートしていないブラウザでは従来のJPEG画像が表示されます。
遅延読み込み(Lazy Load)の実装方法
遅延読み込みは、ページの初期表示時に画面に見えていない画像の読み込みを遅らせ、ユーザーがスクロールして画像が表示される直前に読み込む技術です。
この手法により、初期ページ読み込み速度が大幅に改善され、特に画像が多いページで効果を発揮します。
遅延読み込みの実装方法として、最も簡単なのはHTMLのloading属性を使用する方法です。imgタグにloading="lazy"を追加するだけで、ブラウザが自動的に遅延読み込みを処理してくれます。
<img src="image.jpg" alt="説明文" loading="lazy">
この方法は主要なブラウザでサポートされており、JavaScriptを使わずに実装できるため推奨されます。
より細かい制御が必要な場合は、Intersection Observer APIを使用したカスタム実装や、LazySizesなどのJavaScriptライブラリを活用する方法もあります。
ただし、ファーストビュー内の画像には遅延読み込みを適用せず、すぐに表示されるようにすることが重要です。
特にLCP(最大コンテンツの描画)の対象となる画像に遅延読み込みを適用すると、かえってパフォーマンスが悪化する可能性があるため注意しましょう。
よくある失敗パターンと対処法

画像最適化を進める際、よくある失敗パターンを事前に理解しておくことで、効率的に改善を進められます。
主な失敗パターンは以下のとおりです。
主な失敗パターン
- ❶ 過度な圧縮で画質が劣化する
- ❷ alt属性にキーワードを詰め込みすぎる
- ❸ CDN導入で逆に遅くなる
それぞれの失敗例と適切な対処法を見ていきましょう。
過度な圧縮で画質が劣化する
画像の軽量化を優先するあまり、圧縮率を上げすぎて画質が著しく劣化してしまうケースがあります。
特に商品写真や人物写真では、過度な圧縮によってノイズやブロックノイズが目立ち、かえってユーザー体験を損なう結果となります。
ECサイトにおいては、画質の悪い商品写真は購入意欲を低下させる要因となるため、適切なバランスが重要です。
対処法としては、圧縮後の画像を必ず実際のデバイスで確認し、スマートフォンとPCの両方で問題ないかをチェックすることが挙げられます。
また、重要な画像とそうでない画像で圧縮率を変え、例えばアイキャッチ画像は品質を保ち、補助的な図解は軽量化を優先するなど、メリハリをつけることも効果的です。
品質と軽量化のバランスを見極めるには、複数の圧縮率で試し、ファイルサイズと画質の両方を比較しながら最適な設定を見つけましょう。
alt属性にキーワードを詰め込みすぎる
SEO効果を期待するあまり、alt属性に関連キーワードを不自然に詰め込んでしまうケースがあります。
「SEO 画像 最適化 方法 効果 施策」のようなalt属性は、検索エンジンにスパムと判断される可能性があり、逆効果となります。
また、スクリーンリーダーを使用するユーザーにとっても、意味のないキーワードの羅列は理解を妨げる要因となります。
適切な対処法は、alt属性には画像の内容を正確に説明する自然な文章を記述し、その中に関連キーワードが含まれる程度に留めることです。
例えば「SEO対策における画像最適化の手順を示したフローチャート」のように、画像の内容を具体的に説明することで、自然にキーワードが含まれます。
視覚障害のあるユーザーがスクリーンリーダーで読み上げた際に、画像の内容が理解できるかどうかを基準に考えることが大切です。
CDN導入で逆に遅くなる
CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)は画像配信を高速化する有効な手段ですが、設定を誤ると逆にパフォーマンスが低下することがあります。
特に小規模サイトや地域限定のサービスでは、CDNの初期接続時間がかえって表示速度を遅くする場合があります。
また、適切なキャッシュ設定がされていないと、毎回オリジンサーバーへのアクセスが発生し、CDNの利点が活かされません。
対処法としては、まずPageSpeed InsightsやGTmetrixなどのツールで、CDN導入前後のパフォーマンスを測定し、実際に改善されているかを確認することが重要です。
CDNを使用する場合は、適切なキャッシュ期間を設定し、画像などの静的ファイルは長期間キャッシュされるようにしましょう。
小規模サイトや特定地域向けのサービスでは、CDN導入よりもサーバー自体の高速化や画像最適化を優先したほうが効果的な場合もあります。
自社サイトの規模やターゲットユーザーの地域分布を考慮して、CDN導入の必要性を判断しましょう。
画像最適化の効果測定と改善サイクル

画像最適化は一度実施して終わりではなく、継続的な測定と改善が重要です。
効果測定の方法は以下のとおりです。
- PageSpeed Insightsで確認すべき3つの指標
- Search Consoleで画像検索パフォーマンスを分析する
- A/Bテストで最適な画像サイズを見つける
データに基づいた改善サイクルを回すことで、持続的なパフォーマンス向上が実現できます。それぞれ詳しく解説します。
PageSpeed Insightsで確認すべき3つの指標
Google PageSpeed Insightsは、Webページのパフォーマンスを測定する無料ツールです。
画像最適化の効果を測定する際、特に注目すべき指標は以下の3つです。
| 指標 | 内容 | 目標値 | 画像最適化との関連 |
|---|---|---|---|
| LCP(Largest Contentful Paint) | 最大コンテンツの描画時間 | 2.5秒以下 | メイン画像のサイズと読み込み速度に直接影響 |
| CLS(Cumulative Layout Shift) | レイアウトの安定性 | 0.1以下 | 画像の幅と高さ属性の指定が重要 |
| FID(First Input Delay) | 最初の入力遅延 | 100ms以下 | 画像の遅延読み込みの影響を受ける |
これらの指標を定期的にモニタリングし、改善箇所を特定することで、効果的な最適化が可能になります。
PageSpeed Insightsは、具体的な改善提案も表示してくれるため、それらを優先順位に従って実施していくとよいでしょう。
モバイルとデスクトップの両方で測定し、特にモバイルでのパフォーマンスを重視することが大切です。
Search Consoleで画像検索パフォーマンスを分析する
Google Search Consoleでは、画像検索からのトラフィックを詳細に分析できます。
「検索パフォーマンス」レポートで検索タイプを「画像」に切り替えることで、どのような検索クエリで画像が表示され、クリックされているかを確認できます。
この データを分析することで、どのような画像コンテンツが効果的か、どのキーワードで画像検索されているかが把握できます。
分析のポイントとしては、表示回数は多いがクリック率が低い画像を特定し、alt属性やファイル名を改善する、クリック率の高い画像の特徴を分析し、他の画像にも応用する、競合サイトが上位表示されている画像検索クエリを見つけ、自社でも強化する領域を決めるなどが挙げられます。
画像検索からの流入が増えれば、サイト全体のトラフィック増加につながるため、定期的にパフォーマンスをチェックし、改善を続けることが重要です。
A/Bテストで最適な画像サイズを見つける
理論的な推奨値はあるものの、最適な画像サイズは業種やターゲットユーザーによって異なります。
A/Bテストを実施することで、自社サイトに最適な画像サイズや表示方法を見つけることができます。
例えば、同じ商品ページで画像サイズを大きくしたバージョンと小さくしたバージョンを用意し、コンバージョン率やページ滞在時間を比較します。
テストする要素としては、アイキャッチ画像のサイズ(大きい方が注目されるか、軽量な方が離脱率が低いか)、記事内画像の配置(左寄せ・中央・全幅のどれが読みやすいか)、サムネイル画像のサイズ(クリック率が高いサイズはどれか)などが考えられます。
Google OptimizeやVWO、Adobe Targetなどのツールを使用すれば、簡単にA/Bテストを実施できます。
テスト期間は最低でも2週間程度設け、統計的に有意な差が出るまでデータを収集しましょう。
FAQ|画像最適化のよくある質問10選
画像最適化に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
画像は何枚まで使っていい?
画像の枚数自体に厳密な上限はありませんが、ページ全体のパフォーマンスを考慮する必要があります。
一般的に、1ページあたりの画像ファイルサイズの合計は、モバイルで1〜2MB、デスクトップで2〜3MB以内に収めることが推奨されます。
記事の長さや内容にもよりますが、3000〜5000文字の記事であれば、5〜10枚程度の画像が適切でしょう。
重要なのは枚数ではなく、各画像が記事の理解を助け、ユーザー体験を向上させているかどうかです。
装飾目的だけの画像は最小限に抑え、コンテンツに価値を加える画像を選択しましょう。
スマホとPCで画像を出し分けるべき?
デバイスごとに最適な画像を配信することは、パフォーマンス向上に非常に効果的です。
HTMLのsrcset属性や<picture>要素を使用すれば、デバイスの画面サイズに応じて異なる画像を配信できます。
例えば、スマートフォンには800px幅の画像を、タブレットには1200px幅、デスクトップには1600px幅の画像を配信するといった設定が可能です。
特にモバイルユーザーの通信量を削減できるため、ユーザー体験の向上とSEO評価の改善につながります。
WordPressなどのCMSを使用している場合、自動的にレスポンシブ対応の画像を生成する機能が標準で備わっているケースも多いため、積極的に活用しましょう。
著作権フリー素材のSEO効果は?
著作権フリーの素材を使用すること自体は、SEOに直接的な悪影響を与えません。
ただし、多くのサイトで使用されている汎用的な素材よりも、オリジナルの画像の方がSEO効果は高い傾向にあります。
Googleは独自性のあるコンテンツを評価するため、競合サイトと同じストック写真を使うよりも、自社で撮影した写真や独自に作成した図解の方が差別化につながります。
予算や時間の制約で著作権フリー素材を使用する場合は、できるだけ独自の編集を加える、テキストオーバーレイで独自情報を追加する、複数の素材を組み合わせて新しいビジュアルを作成するなどの工夫をすることで、独自性を高められます。
古い記事の画像も最適化すべき?
過去の記事の画像も、積極的に最適化すべきです。
特にアクセス数の多い記事や、検索順位が上位に近い記事の画像を優先的に最適化することで、サイト全体のパフォーマンス向上が期待できます。
古い記事の画像最適化を行う際は、以下の手順で進めるとよいでしょう。
まず、Google Analyticsでアクセス数の多いページを特定し、そのページの画像を優先的に最適化します。
次に、PageSpeed Insightsで低スコアのページを見つけ、画像が原因となっている場合は改善を行います。
最後に、時間をかけて全記事の画像を順次最適化していき、長期的なサイト改善につなげます。
画像の最適化は一度実施すれば継続的に効果が得られるため、時間をかけてでも取り組む価値があります。
画像まわりの改善を「ちゃんとやり切りたい」企業さまへ
画像を圧縮したり、形式を変えたりしてみたものの、
-
PageSpeed Insightsのスコアがなかなか上がらない
-
どのページから手をつければいいのか分からない
-
社内で試してみても、効果検証まで手が回らない
こうしたお悩みは、珍しいものではありません。
正直なところ、画像まわりは「あとでやろう」と後回しにされがちで、その結果チャンスを逃しているサイトも多く見られます。
当社では、単に画像を軽くするだけでなく、
-
どのページを優先して改善すべきかの整理
-
画像最適化とCore Web Vitals改善のセット設計
-
施策前後の計測とレポート
までを一括でご支援しています。
「とりあえず対処」ではなく、SEO対策とユーザー体験の両方を底上げするための設計から一緒に伴走するスタイルです。
もし、
自社だけでの改善に限界を感じている
サイト全体を見直したうえで画像を最適化したい
というお気持ちがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
貴社のサイト状況をヒアリングしたうえで、無理のない改善ステップをご提案します。
まとめ

SEO対策における画像最適化は、ユーザー体験の向上と検索順位の改善に直結する重要な施策です。
適切なファイル形式の選択、ファイルサイズの削減、alt属性の設定など、基本的な最適化を行うだけでも、サイトのパフォーマンスは大きく改善されます。
画像最適化で押さえるべき重要ポイントを再確認しましょう。
画像最適化で押さえるべき重要ポイント
- ❶ ユーザー体験を最優先に考え、表示速度とビジュアル品質のバランスを取る
- ❷ WebP形式への変換や遅延読み込みなど、最新技術を積極的に活用する
- ❸ PageSpeed InsightsやSearch Consoleでデータを測定し、継続的に改善する
- ❹ 過度な最適化やキーワード詰め込みなど、よくある失敗パターンを避ける
画像最適化は一度実施して終わりではなく、定期的な見直しと改善が必要です。
新しい記事を公開する際は最初から最適化された画像を使用し、既存記事についても優先順位をつけて順次改善していくことで、サイト全体のSEO効果を高められるでしょう。
今回ご紹介した方法を参考に、自社サイトの画像最適化に取り組んでみてください。小さな改善の積み重ねが、大きな成果につながるはずです。