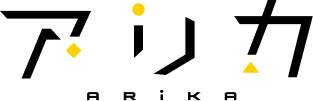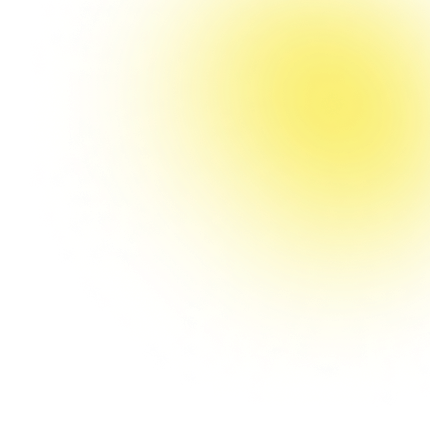Blog
ブログ
2025.10.28
SEO
検索上位を狙うSEO競合分析のやり方|勝てるキーワードの見つけ方と戦略を徹底解剖
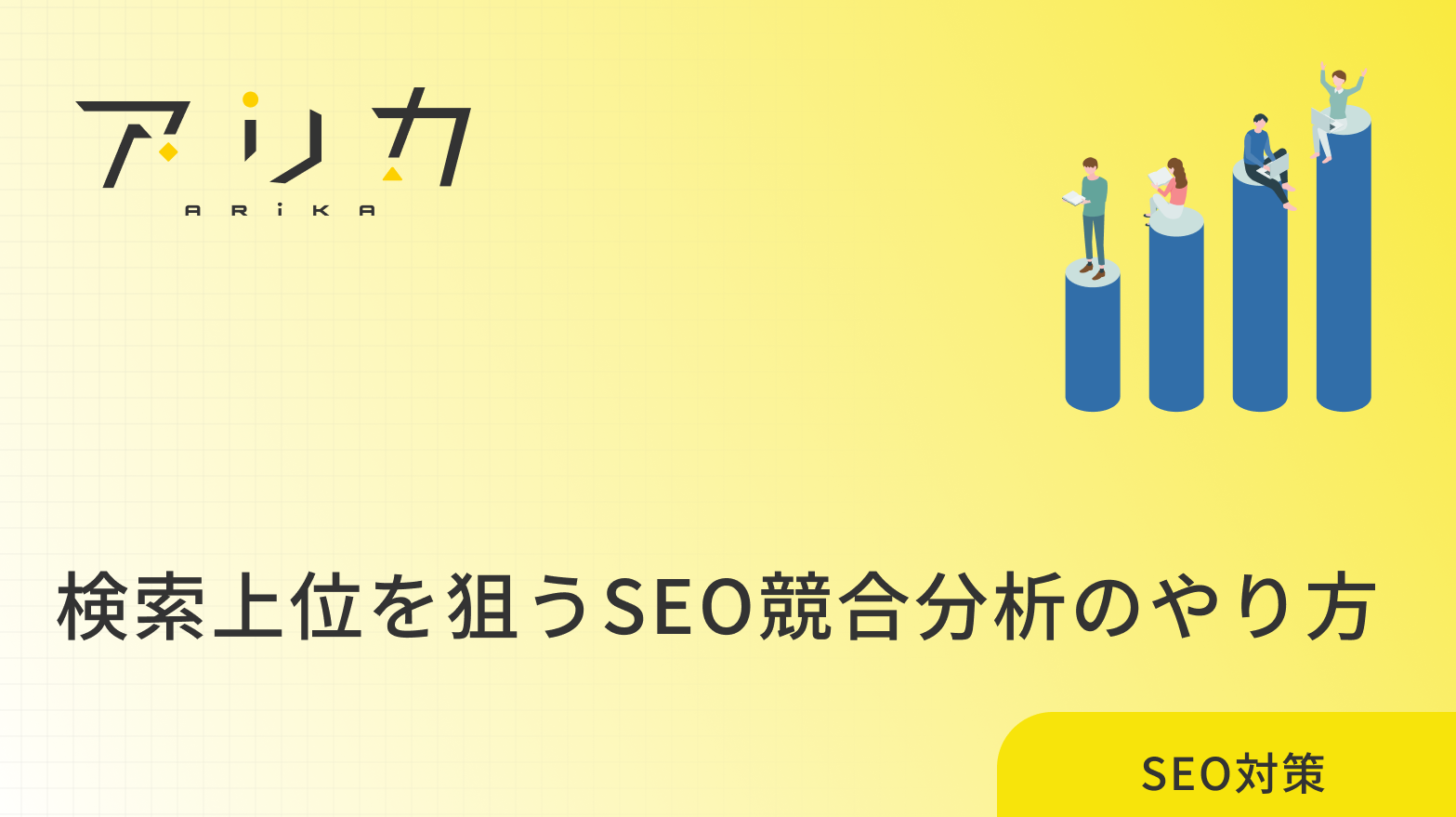
「SEO対策を始めたけれど、なかなか検索順位が上がらない…」
「競合サイトはなぜ上位表示されているのだろう?」
「どうすれば競合に勝てる記事が書けるのか分からない」
このような悩みを抱えているWeb担当者やマーケターの方は少なくありません。実際、SEO対策において競合分析を行わないまま施策を進めてしまうと、効果的な戦略を立てることが難しくなります。
競合分析を正しく実施することで、上位表示されているサイトの強みや弱点を把握し、自社サイトの改善点が明確になります。
本記事では、SEOにおける競合分析の基本から、具体的な実施手順、無料・有料ツールの使い方、そして分析結果を実際のSEO戦略に落とし込む方法まで、実践的な内容を詳しく解説します。
競合分析をマスターして、検索上位を目指す第一歩を踏み出しましょう。
SEO対策の競合分析とは?なぜ必要なのか
SEO対策を成功させるためには、競合サイトの戦略を理解することが欠かせません。ここでは、競合分析の基本的な定義と、なぜそれが重要なのかを見ていきましょう。
競合分析とは?
競合分析とは、検索エンジンで上位表示されている他社サイトの戦略や施策を調査・分析することです。
具体的には、以下のような要素を分析します。
- どのようなキーワードで上位表示されているか
- コンテンツの質や構成はどうなっているか
- 被リンクの数や質はどの程度か
- サイト全体のドメインパワーはどれくらいか
- 更新頻度やコンテンツ追加のペースはどうか
SEOにおける競合とは、必ずしも事業上の直接的な競合企業だけを指すわけではありません。
同じキーワードで検索結果に表示されるすべてのサイトが、SEO上の競合となります。
例えば、飲食店を運営している企業が「パスタ レシピ」というキーワードで記事を作成する場合、競合となるのは他の飲食店だけでなく、料理レシピサイトや個人ブログなども含まれます。
SEOで競合分析をしないと起こるリスク
競合分析を行わずにSEO対策を進めると、いくつかの重大なリスクが生じます。
まず、どの程度の品質のコンテンツが求められているか分からないという問題があります。検索上位に表示されるには、既に上位表示されているコンテンツと同等以上の価値を提供する必要があります。競合分析をしないと、その基準が見えません。
次に、無駄な努力をしてしまう可能性があります。例えば、ドメインパワーが非常に強い大手サイトが独占しているキーワードに対して、新規サイトが同じアプローチで挑んでも、上位表示は困難です。
また、競合が既に網羅しているトピックを同じように書いても、差別化ができず検索エンジンから評価されにくくなります。独自性のあるコンテンツを作るためにも、競合分析は不可欠です。
さらに、トレンドや検索ニーズの変化に気づけないというリスクもあります。競合サイトの動向を定期的にチェックすることで、業界のトレンドや検索ユーザーのニーズの変化を把握できます。
競合分析で得られるメリット
適切な競合分析を行うことで、多くのメリットが得られます。
最大のメリットは、上位表示に必要な要素が明確になることです。競合サイトを分析することで、以下のような情報が手に入ります。
- 必要なコンテンツの文字数や深さ
- ユーザーが求めている情報の種類
- 効果的な見出し構成やキーワードの使い方
- 競合が獲得している被リンクの傾向
また、自社の差別化ポイントが見つかるというメリットもあります。競合が扱っていないトピックや、十分に深掘りしていない領域を発見することで、独自性のあるコンテンツを作成できます。
さらに、効率的なキーワード選定が可能になります。競合が狙っているキーワードの中から、自社でも勝てる可能性が高いキーワードを見極めることができます。
コンテンツ制作の方向性が定まるのも大きなメリットです。どのような切り口やトーンでコンテンツを作れば良いか、競合の成功パターンから学べます。
どのタイミングで競合分析をすべきか
競合分析は、一度行えば終わりではなく、複数のタイミングで実施することが重要です。
新規サイトを立ち上げる際は、必ず競合分析を行いましょう。どのような戦略で進めるべきか、初期の方向性を決めるために不可欠です。
また、新しいキーワードやトピックに取り組む前にも分析が必要です。そのキーワードで上位表示するために何が求められているかを事前に把握することで、効率的なコンテンツ制作ができます。
既存コンテンツのリライトを行う際も、競合分析は有効です。競合サイトがどのように更新しているか、新たにどのような情報を追加しているかを確認することで、リライトの方向性が明確になります。
さらに、定期的なモニタリングとして、月に1回程度は主要キーワードの競合状況をチェックすることをおすすめします。検索結果は常に変動しており、新しい競合の参入や既存競合の戦略変更に気づくためです。
競合分析の重要性の振り返り
- ❶ 競合分析は検索上位表示に必要な要素を明確にするために不可欠
- ❷ 分析をしないと無駄な努力や差別化不足のリスクがある
- ❸ 新規サイト立ち上げ時やコンテンツ作成前、定期的なモニタリングが重要
競合分析の前に準備すべき3つのこと
効果的な競合分析を行うには、事前準備が重要です。ここでは、分析を始める前に整理しておくべき3つのポイントを解説します。
分析対象キーワードの選定
競合分析を始める前に、どのキーワードで分析を行うかを明確にする必要があります。
キーワード選定の基準として、以下の要素を考慮しましょう。
- 自社のビジネスに関連性が高いか
- 検索ボリュームは十分にあるか
- コンバージョンにつながる可能性が高いか
- 現在の自社サイトの実力で勝てる可能性があるか
メインキーワードだけでなく、関連する複数のキーワードでも分析を行うことが推奨されます。例えば「SEO対策」というメインキーワードに対して、「SEO対策 方法」「SEO対策 初心者」「SEO対策 ツール」といった関連キーワードでも競合状況を確認します。
ロングテールキーワードも含めて分析することで、競合が手薄になっている領域を発見できる可能性が高まります。
キーワードの優先順位付けも重要です。すべてのキーワードを同時に分析するのは時間がかかるため、まずはビジネスへの影響が大きいキーワードから着手しましょう。
競合サイトを選ぶ
分析対象とする競合サイトの選定も、事前に行っておく必要があります。
SEOにおける競合は、大きく2種類に分けられます。
- 検索結果での競合:同じキーワードで上位表示されているサイト
- ビジネス上の競合:同じ商品・サービスを提供している企業のサイト
SEO対策の観点では、検索結果での競合を優先的に分析することが重要です。なぜなら、実際に検索順位で競い合う相手だからです。
ただし、ビジネス上の競合も無視できません。同業他社がどのようなSEO戦略を取っているかを把握することで、業界全体のトレンドや自社のポジショニングが見えてきます。
競合サイトの選定数の目安としては、以下が一般的です。
- 詳細分析する競合:3〜5サイト
- 簡易的に把握する競合:10〜20サイト
すべての競合を詳細に分析する必要はなく、特に強力なサイトや参考になるサイトに絞り込んで深く分析することが効率的です。
使用するツール
競合分析には、さまざまなツールを活用することで効率が大幅に向上します。
無料で使えるツールとして、以下のようなものがあります。
- Googleサーチコンソール:自社サイトの検索パフォーマンスを把握
- ラッコキーワード:キーワードの検索意図や関連語を調査
- Ubersuggest:競合のキーワードやトラフィックを簡易的に分析
- SimilarWeb:競合サイトのアクセス数や流入元を推定
有料ツールでは、より詳細な分析が可能になります。
- Ahrefs:被リンク分析やキーワード調査に強い総合ツール
- SEMrush:競合のキーワード戦略を詳細に把握できる
- GRC:検索順位の推移を継続的に追跡
初めて競合分析を行う場合は、まず無料ツールから始めて、必要性を感じたら有料ツールの導入を検討するのが賢明です。
ツールの選定では、自社の予算と分析の目的に合わせて、最適な組み合わせを見つけることが大切です。
競合サイトを分析する具体的な手順
準備が整ったら、実際に競合サイトの分析を進めていきます。ここでは、効率的に競合を特定し、分析対象を絞り込む手順を解説します。
Google検索で上位10サイトをリストアップ
競合分析の第一歩は、対象キーワードでGoogle検索を行い、上位10サイトを確認することです。
検索を行う際の注意点として、以下を押さえておきましょう。
- シークレットモード(プライベートブラウジング)を使用して、パーソナライズされた検索結果の影響を排除する
- 地域性のあるキーワードの場合は、対象地域での検索結果を確認する
- モバイルとPCの両方で検索結果を確認する(順位が異なる場合がある)
上位10サイトをスプレッドシートなどにリスト化し、以下の基本情報を記録します。
- サイト名・URL
- 検索順位
- タイトルタグの内容
- メタディスクリプションの内容
- サイトの種類(企業サイト、メディアサイト、個人ブログなど)
この段階では詳細な分析は不要で、まずは全体像を把握することが目的です。
実際の競合と検索結果の競合の違い
リストアップした上位サイトを見ると、ビジネス上の直接的な競合ではないサイトが含まれていることに気づくでしょう。
例えば、「動画編集 PC」というキーワードで検索した場合、以下のようなサイトが上位に表示されます。
- PCメーカーの公式サイト
- 家電量販店のECサイト
- 価格比較サイト
- 個人ブログや専門メディア
- 動画編集スクールのサイト
これらはビジネスモデルが異なりますが、SEO上は同じキーワードで競合しています。
この違いを理解することで、以下のような戦略的判断ができます。
- 大手ECサイトと同じアプローチでは勝てないため、別の切り口を探す
- 個人ブログが上位にいる場合は、自社でも勝てる可能性が高い
- 企業の公式サイトが独占している場合は、ロングテールキーワードを狙う
ビジネス上の競合だけを見るのではなく、検索結果に実際に表示されているサイトを分析することで、現実的なSEO戦略が立てられます。
複数キーワードで競合を洗い出す
1つのキーワードだけで競合を判断するのは不十分です。関連する複数のキーワードで検索を行い、繰り返し上位に表示されるサイトを特定しましょう。
例えば、「ホームページ 集客」というテーマであれば、以下のようなキーワードで検索します。
- ホームページ 集客
- ホームページ 集客方法
- ホームページ アクセス数 増やす
- Webサイト 集客 施策
- SEO 集客
これらの複数のキーワードで繰り返し上位に表示されるサイトは、そのテーマ全体で強い影響力を持つ真の競合と言えます。
逆に、特定のキーワードでのみ上位表示されているサイトは、そのキーワードに特化した強みを持っているか、偶然上位表示されている可能性があります。
複数キーワードでの分析により、競合の全体的な戦略や強み・弱みが見えてきます。
競合候補を絞り込む
複数のキーワードで洗い出した競合候補の中から、詳細に分析する対象を絞り込みます。
絞り込みの基準として、以下のポイントを考慮しましょう。
- 複数のキーワードで繰り返し上位表示されている
- 自社と同程度のドメインパワーまたはやや上のレベル
- コンテンツの質が高く、参考になる
- 自社とビジネスモデルが近い(比較分析しやすい)
特に重要なのは、自社と同程度のレベルの競合を選ぶことです。大手企業のサイトばかりを分析しても、リソースや予算が大きく異なるため、そのまま参考にできないことが多いためです。
最終的に、詳細分析する競合は3〜5サイト程度に絞り込むのが効率的です。それ以外のサイトは、簡易的な情報収集にとどめておきましょう。
競合サイトで分析すべき5つのポイント
分析対象の競合が決まったら、具体的にどの要素を見ていくかを理解しましょう。ここでは、SEO観点で重要な5つの分析ポイントを詳しく解説します。
記事の文字数・構成・見出し構造
競合コンテンツの構造を分析することで、上位表示に必要なコンテンツの質と量が見えてきます。
文字数の確認では、競合記事の文字数をツールで計測します。無料の文字数カウントツールや、ブラウザの拡張機能を使うと便利です。
ただし、文字数が多ければ良いというわけではありません。重要なのは、ユーザーの検索意図に対して十分な情報を提供できているかです。
見出し構造の分析では、以下の点を確認しましょう。
- H2、H3、H4などの見出しタグの使い方
- どのようなトピックを扱っているか
- 見出しにキーワードがどう含まれているか
- 全体の論理的な流れはどうなっているか
競合の見出し構造を参考にしつつ、自社ではさらに詳しく解説できる部分や、競合が扱っていない視点を見つけることが重要です。
コンテンツの構成要素として、以下もチェックします。
- 導入文の書き方(問題提起や共感の仕方)
- 本文の展開方法(論理的な流れ)
- 図表や画像の使用頻度と質
- 箇条書きやリストの活用
- まとめ部分の構成
- CTA(行動喚起)の配置
タイトルとメタディスクリプションの傾向
タイトルタグとメタディスクリプションは、検索結果でのクリック率に大きく影響する重要な要素です。
競合のタイトルタグを分析する際は、以下の点に注目しましょう。
- 文字数(30〜35文字程度が一般的)
- キーワードの配置(前方に配置されているか)
- 数字の使用(「5つの方法」「2025年最新」など)
- 魅力的なフレーズ(「完全ガイド」「徹底解説」など)
- ターゲット層への呼びかけ(「初心者向け」「プロが教える」など)
メタディスクリプションでは、以下を確認します。
- 文字数(120〜130文字程度)
- 記事の内容を的確に要約しているか
- ユーザーのベネフィットが明確か
- キーワードの自然な含有
上位サイトのタイトルに共通するパターンを見つけ、それを参考にしながら自社の独自性を加えることで、効果的なタイトルを作成できます。
コンテンツの質と独自性の確認方法
単に文字数や構成を真似するだけでは、上位表示は難しくなっています。コンテンツの質と独自性を評価することが重要です。
コンテンツの質を評価する観点として、以下があります。
- 情報の正確性:データや事実に基づいているか
- 情報の網羅性:ユーザーの疑問に十分答えているか
- 情報の新しさ:最新の情報が反映されているか
- 専門性:その分野の専門知識が示されているか
- 信頼性:著者の経歴や情報源が明示されているか
独自性の評価では、以下をチェックします。
- オリジナルの調査データや事例があるか
- 独自の視点や切り口があるか
- 実体験に基づく情報があるか
- 他のサイトにはない詳細な解説があるか
競合が提供している価値を理解した上で、自社ならではの強みや経験を活かして、さらに価値の高いコンテンツを作ることが差別化につながります。
被リンク数とドメインパワーを調べる
被リンクとドメインパワーは、検索順位に大きな影響を与える要素です。
被リンク数の調査では、AhrefsやMozなどのツールを使用して、以下の情報を取得します。
- 被リンクの総数
- 参照ドメイン数(何サイトからリンクされているか)
- 被リンクの質(権威性の高いサイトからのリンクか)
- リンク元のコンテンツの関連性
ドメインパワーの指標として、以下を確認します。
- Ahrefsのドメインレーティング(DR)
- MozのドメインオーソリティDA)
- その他のSEOツールの独自指標
競合のドメインパワーが自社より大幅に高い場合、同じキーワードで正面から勝負するのは困難です。その場合は、ロングテールキーワードや競合が手薄な領域を狙う戦略が有効です。
逆に、競合と同程度またはそれ以下のドメインパワーで上位表示されているサイトがあれば、コンテンツの質で勝負できる可能性が高いと言えます。
更新頻度とコンテンツ追加のペース
競合サイトの更新状況を把握することで、業界で求められるコンテンツ更新のペースが分かります。
確認すべき項目は以下の通りです。
- 新規記事の公開頻度(週何本、月何本)
- 既存記事のリライト頻度
- 最終更新日の表示の有無
- 季節やトレンドに合わせた更新があるか
競合が頻繁に更新している場合、検索エンジンはそのサイトを「新鮮な情報を提供している」と評価している可能性があります。
ただし、やみくもに更新すれば良いわけではありません。ユーザーにとって価値のある更新かどうかが重要です。
競合の更新パターンから、以下のような戦略的示唆が得られます。
- トレンドキーワードへの対応速度
- 季節性のあるコンテンツの準備時期
- リライトの優先順位の付け方
- コンテンツの追加・削除の判断基準
無料でできる競合分析のやり方【ツール別】
予算が限られている場合でも、無料ツールを組み合わせることで効果的な競合分析が可能です。ここでは、代表的な無料ツールの活用方法を解説します。
Googleサーチコンソールでの競合調査
Googleサーチコンソールは、自社サイトのデータを分析するツールですが、間接的に競合の戦略を推測するためにも活用できます。
「検索パフォーマンス」レポートでは、以下の情報を確認できます。
- 自社サイトがどのキーワードで表示されているか
- 各キーワードでの平均掲載順位
- クリック率(CTR)
- 表示回数
この情報から、自社が上位表示できていないキーワードを特定し、そのキーワードで実際に検索して競合を確認するという使い方ができます。
また、自社サイトと競合サイトのCTRを比較することで、タイトルやメタディスクリプションの改善ポイントが見えてきます。自社より下位なのにCTRが高い場合、競合のタイトルやディスクリプションがより魅力的である可能性があります。
「リンク」レポートでは、自社サイトへの被リンク状況を確認できます。競合サイトと比較して被リンクが少ない場合、リンク獲得施策の必要性が明確になります。
ラッコキーワードで検索意図を分析
ラッコキーワードは、キーワードの検索意図や関連語を調査できる無料ツールです。
主な活用方法は以下の通りです。
サジェストキーワードの取得では、メインキーワードを入力すると、Googleのサジェスト(検索候補)に表示される関連キーワードを一覧で取得できます。競合がどのようなキーワードで記事を作成しているかを把握する際に便利です。
見出し抽出機能では、特定のURLを入力すると、そのページの見出し構造を抽出できます。競合記事の構成を素早く把握し、どのようなトピックを扱っているかを一目で確認できるのが特徴です。
Q&Aサイトの抽出では、Yahoo!知恵袋や教えて!gooなどのQ&Aサイトから、関連する質問を抽出できます。ユーザーが実際に抱えている疑問を把握し、それに答えるコンテンツを作ることで、競合との差別化が可能になります。
ラッコキーワードで得た情報を基に、競合が扱っていないトピックや、十分に答えていない質問を見つけ出しましょう。
Ubersuggestの無料機能を使った分析
Ubersuggestは、無料プランでも競合のキーワードやトラフィックを簡易的に分析できるツールです。
ドメイン分析機能では、競合サイトのURLを入力することで、以下の情報を取得できます。
- 月間推定トラフィック数
- ドメインスコア(ドメインパワーの指標)
- 被リンク数
- 上位表示しているキーワード数
無料プランでは制限がありますが、競合の全体的な強さを把握するには十分です。
キーワード分析では、特定のキーワードを入力すると、以下の情報が得られます。
- 検索ボリューム
- SEO難易度
- クリック単価(CPC)
- 関連キーワード
SEO難易度を確認することで、自社が勝てる可能性があるキーワードかどうかを判断できます。
コンテンツアイデア機能では、特定のキーワードで上位表示されているコンテンツを一覧表示し、各記事の推定トラフィックやソーシャルシェア数を確認できます。どのようなコンテンツが評価されているかを把握するのに便利です。
無料ツールでの競合分析の振り返り
- ❶ Googleサーチコンソールで自社の弱点を見つけて競合を特定
- ❷ ラッコキーワードで競合の見出し構成と検索意図を把握
- ❸ Ubersuggestで競合の全体的な強さとキーワード難易度を確認
有料ツールを使った本格的な競合分析
本格的にSEO対策を進める場合、有料ツールの導入を検討する価値があります。ここでは、代表的な有料ツールの活用方法と、導入のタイミングについて解説します。
Ahrefsで被リンクとキーワードを徹底調査
Ahrefsは、世界最大級の被リンクデータベースを持つSEO総合ツールです。月額料金は約12,000円からとなりますが、競合分析においては非常に強力な機能を提供します。
サイトエクスプローラー機能では、競合サイトのURLを入力することで、以下の詳細情報を取得できます。
- 被リンクの総数と参照ドメイン数
- ドメインレーティング(DR)とURLレーティング(UR)
- オーガニックトラフィックの推定値
- 上位表示しているキーワード一覧
- トラフィックの推移グラフ
特に強力なのが被リンク分析機能です。競合がどのようなサイトからリンクを獲得しているかを詳細に把握し、自社のリンク獲得戦略に活かせます。
コンテンツギャップ分析では、自社サイトと競合サイトを比較し、競合が上位表示しているが自社が表示されていないキーワードを洗い出せます。これにより、取り組むべきキーワードの優先順位が明確になります。
トップページ分析では、競合サイトの中で最もトラフィックを集めているページを特定できます。どのようなコンテンツが成功しているかを把握し、自社のコンテンツ戦略に反映させましょう。
Ahrefsの活用により、無料ツールでは得られない詳細な競合情報を取得でき、より戦略的なSEO対策が可能になります。
SEMrushで競合の流入キーワードを把握
SEMrushは、キーワード調査と競合分析に特化したツールです。月額料金は約13,000円からとなります。
ドメイン概要レポートでは、競合サイトのオーガニック検索とリスティング広告の両方のパフォーマンスを一覧で確認できます。以下の情報が得られます。
- オーガニック検索の推定トラフィック
- 上位表示キーワード数
- 有料広告のキーワード数
- 広告費の推定額
オーガニックリサーチ機能では、競合が上位表示している全キーワードを一覧表示し、各キーワードでの順位、検索ボリューム、推定トラフィックを確認できます。
競合がどのキーワードで成功しているかを把握し、自社も同じキーワードで勝負すべきか、別のキーワードを狙うべきかを判断できます。
キーワードギャップ分析では、最大5つのドメインを同時に比較し、以下の情報を視覚化できます。
- 全サイトで共通して上位表示しているキーワード
- 自社だけが上位表示していないキーワード
- 自社だけが上位表示しているキーワード
- 競合同士で重複しているキーワード
広告調査機能では、競合がどのようなリスティング広告を出稿しているかを確認できます。広告のコピー、ランディングページ、出稿期間などを分析することで、競合のマーケティング戦略全体を把握できます。
GRCで検索順位の変動を追跡
GRCは、検索順位を自動で追跡し、変動を記録する国産ツールです。月額料金は約500円からと、他の有料ツールと比較して非常にリーズナブルです。
主な機能は以下の通りです。
- 指定したキーワードの検索順位を毎日自動取得
- 順位変動をグラフで視覚化
- Google、Yahoo、Bingの3つの検索エンジンに対応
- 競合サイトの順位も同時に追跡可能
GRCの最大の利点は、長期的な順位変動のトレンドを把握できることです。
自社と競合の順位を同時に追跡することで、以下のような分析ができます。
- 競合がコンテンツを更新したタイミングで順位が上がったか
- Googleのアルゴリズムアップデートによる影響の違い
- 季節性による順位変動のパターン
- 自社の施策の効果が現れるまでの期間
メモ機能を活用すれば、コンテンツ更新や被リンク獲得などの施策を実施した日付を記録できます。施策と順位変動の関係を後から分析する際に便利です。
順位下落アラート機能では、設定した順位よりも下がった場合に通知を受け取れます。競合サイトの急激な順位上昇にも素早く気づけるため、迅速な対応が可能になります。
有料ツールを使うべきタイミングと費用対効果
有料ツールは強力ですが、すべての企業にとって必須というわけではありません。導入すべきタイミングと費用対効果を見極めることが重要です。
有料ツールの導入を検討すべきタイミングは以下の通りです。
- 無料ツールでは取得できない詳細データが必要になった
- 複数のサイトやキーワードを継続的に管理する必要がある
- SEOに本格的に投資する予算が確保できた
- 競合が強力で、詳細な分析なしでは勝てない状況
- 社内でSEOの重要性が認識され、データに基づく意思決定が求められている
費用対効果の考え方として、ツールの月額費用を、それによって獲得できる追加の売上や利益と比較する必要があります。
例えば、月額12,000円のAhrefsを導入し、それによって新たに月間10万円の売上増加につながるキーワードを発見できれば、十分に費用対効果は高いと言えます。
初めて有料ツールを導入する場合のおすすめの順序は以下の通りです。
- GRC(月額500円〜):まず検索順位の追跡から始める
- Ubersuggest有料版(月額3,000円程度):より詳細なキーワード分析が必要になったら
- AhrefsまたはSEMrush(月額12,000円〜):本格的な競合分析が必要になったら
段階的に導入することで、費用を抑えながら必要な機能を見極められます。
競合分析でよくある5つの失敗と対策
競合分析を行う際、多くの人が陥りがちな失敗パターンがあります。ここでは、代表的な失敗例とその対策を解説します。
競合の真似だけで終わってしまう
競合分析で最もよくある失敗は、競合のコンテンツをそのまま真似してしまうことです。
競合と同じ内容のコンテンツを作っても、検索エンジンは後発のコンテンツを高く評価しません。なぜなら、既に同じ情報が存在する場合、新たに追加する価値が低いと判断されるためです。
競合分析の目的は真似することではなく、競合を理解した上で差別化することだと認識しましょう。
対策として、以下のアプローチを取りましょう。
競合の成功パターンを参考にしつつ、自社独自の要素を必ず加えます。以下のような差別化要素を盛り込みましょう。
- 自社の専門知識や経験に基づく独自の視点
- オリジナルの調査データや事例
- より詳細で実践的な情報
- 最新のトレンドや法改正の反映
- 特定のターゲット層に特化した内容
「競合がやっているから」ではなく「なぜ競合がそのアプローチを取っているのか」を考え、その背景にあるユーザーニーズを理解することが重要です。
データ収集に時間をかけすぎる
完璧なデータを集めようとして、分析に膨大な時間をかけてしまうのも典型的な失敗です。
競合分析は手段であり目的ではありません。最終的な目標は、分析結果を活かして自社のSEO施策を改善し、成果を上げることです。
データ収集に時間をかけすぎると、以下のような問題が生じます。
- 実際の施策実行が遅れる
- 市場の変化に対応できない
- チームのモチベーションが低下する
- 費用対効果が悪化する
80%の完成度で分析を終え、残りの20%は実際に施策を進めながら補完していくという考え方が効率的です。
対策として、以下を実践しましょう。
分析の目的と範囲を明確にし、必要最小限のデータに絞ります。「この分析で何を明らかにしたいのか」を常に意識しましょう。
分析に使う時間を事前に決めておきます。例えば「1キーワードあたり2時間以内」「週の分析作業時間は5時間まで」といった制限を設けることで、効率的に進められます。
テンプレートやツールを活用して、データ収集を自動化・効率化します。同じ作業を毎回手作業で行うのは時間の無駄です。
自社の強みを無視した戦略になる
競合分析に没頭するあまり、自社の強みや独自性を見失ってしまう失敗もよくあります。
競合が強い領域で無理に戦うのではなく、自社の強みが活きる領域を見つけることが重要です。
例えば、以下のような自社の強みを活かせる戦略を考えましょう。
- 専門性:特定分野の深い知識や経験を活かした専門的コンテンツ
- 地域性:ローカルSEOで地域に特化した情報提供
- 顧客との関係性:実際の顧客の声や事例を豊富に掲載
- スピード:トレンドに素早く対応した記事作成
- ニッチ市場:大手が参入していない特定のターゲット層への特化
競合ができないこと、やっていないことの中で、自社ができることを見つけるのが差別化の基本です。
対策として、競合分析と並行して自社分析も行いましょう。以下の質問に答えることで、自社の強みが明確になります。
- 自社にしかない知識や経験は何か
- 顧客から特に評価されているポイントは何か
- 自社が最も得意とする分野は何か
- 自社のリソース(人材、時間、予算)で現実的に実行できることは何か
分析結果を活用できず放置する
せっかく詳細な競合分析を行っても、その結果を実際の施策に活かせず放置してしまうのも大きな問題です。
分析レポートを作成しただけで満足してしまい、具体的なアクションにつながらないケースは非常に多く見られます。
この問題が起こる原因は以下の通りです。
- 分析結果が抽象的で、何をすべきか明確でない
- 実行可能なアクションプランに落とし込めていない
- 担当者や期限が決まっていない
- 優先順位が不明確で、どこから手をつけるべきか分からない
対策として、分析レポートには必ず「アクションプラン」のセクションを設け、具体的な施策に落とし込みます。
アクションプランには以下の要素を含めましょう。
- 実施する具体的な施策内容
- 優先度(高・中・低)
- 担当者
- 期限
- 必要なリソース
- 期待される成果
また、定期的にアクションプランの進捗を確認する機会を設けることも重要です。週次または月次のミーティングで、施策の実施状況と成果を確認しましょう。
競合を間違えて選定してしまう
分析すべき競合を間違えて選定してしまうのも、よくある失敗の一つです。
典型的な誤った競合選定のパターンは以下の通りです。
ビジネス上の競合だけを分析してしまうケースでは、実際に検索結果で競合しているサイトを見落としてしまいます。SEOでは、検索結果に表示されるすべてのサイトが競合となることを忘れないようにしましょう。
大手サイトばかりを分析対象にしてしまうと、自社との規模やリソースの差が大きすぎて、参考にならない場合があります。自社と同程度のレベルの競合も分析対象に含めることが重要です。
特定のキーワードでの競合しか見ていないと、全体像が把握できません。関連する複数のキーワードで競合状況を確認し、総合的に判断しましょう。
対策として、以下のアプローチを取りましょう。
複数のキーワードで検索を行い、繰り返し上位表示されるサイトを競合としてリストアップします。
ドメインパワーが自社と同程度のサイトを優先的に分析します。大手サイトも参考にしますが、直接的な競合としては同レベルのサイトに注目しましょう。
定期的に競合リストを見直し、新規参入者や順位変動があった場合は、分析対象を更新します。市場は常に変化しているため、競合も変わっていきます。
FAQ|SEO競合分析のよくある質問
ここでは、SEO競合分析に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
競合分析は何社くらい調べればいい?
詳細に分析する競合は3〜5社程度が適切です。
あまりに多くの競合を分析しようとすると、時間がかかりすぎて実際の施策実行が遅れてしまいます。
推奨される分析対象数は以下の通りです。
- 詳細分析する競合:3〜5社(見出し構成、コンテンツの質、被リンクなどを深く分析)
- 簡易的に確認する競合:10〜20社(基本情報と順位のみ記録)
詳細分析の対象は、以下の基準で選びましょう。
- 複数のキーワードで繰り返し上位表示されている
- 自社と同程度のドメインパワーを持つ
- コンテンツの質が高く参考になる
- ビジネスモデルが自社と近い
最も重要なのは、選んだ競合を継続的に追跡し、変化を把握することです。
多くの競合を浅く分析するよりも、少数の競合を深く継続的に分析する方が効果的です。
無料ツールだけでも十分に分析できる?
初期段階であれば、無料ツールだけでも十分に価値のある分析が可能です。
無料ツールでできることは以下の通りです。
- 検索結果での競合の特定
- 競合サイトの見出し構成の把握
- 基本的なキーワード調査
- 自社サイトのパフォーマンス測定
- 簡易的なトラフィック推定
一方、無料ツールの限界として以下があります。
- 被リンクの詳細情報が限定的
- キーワードデータの取得数に制限
- 過去データの参照が難しい
- 競合の流入キーワードの全容把握が困難
有料ツールの導入を検討すべきタイミングは以下の通りです。
- 無料ツールでは得られない詳細データが必要になった
- 複数のサイトやキーワードを効率的に管理する必要がある
- SEOに本格的に投資する予算が確保できた
- 競合が強力で、詳細な分析なしでは勝てない
まずは無料ツールから始めて、必要性を感じたら段階的に有料ツールを導入するのが賢明なアプローチです。
競合が強すぎる場合はどうすればいい?
直接的な競合が強すぎる場合は、戦略を変える必要があります。
強力な競合に対抗する戦略は以下の通りです。
ロングテールキーワードを狙うアプローチでは、ビッグキーワードで大手と競合するのではなく、より具体的で検索ボリュームが小さいキーワードを狙います。
例えば、「クレジットカード」というビッグキーワードではなく、「クレジットカード 海外旅行 学生 おすすめ」のようなロングテールキーワードを狙うことで、勝てる可能性が高まります。
ニッチな領域に特化する戦略では、大手が手を出していない特定の分野に集中します。幅広く浅くではなく、狭く深くアプローチすることで、その分野での権威性を確立できます。
地域性を活かした戦略では、全国展開している大手に対して、特定の地域に特化したコンテンツを作成します。ローカルSEOを強化することで、その地域では競合に勝てる可能性があります。
独自の強みを前面に出す戦略では、自社にしかない経験、データ、専門性を活かしたコンテンツを作成します。競合が真似できない独自性があれば、後発でも評価される可能性が高まります。
段階的なアプローチでは、まずは勝てるキーワードで実績を積み、ドメインパワーを高めてから、より競合が激しいキーワードに挑戦するという戦略です。
分析結果が出るまでどのくらいかかる?
基本的な競合分析は1〜2日で完了できますが、分析の深さによって必要な時間は異なります。
分析レベル別の所要時間の目安は以下の通りです。
- 簡易分析(上位サイトのリストアップと基本情報の確認):2〜3時間
- 標準的な分析(3〜5社の詳細分析とレポート作成):1〜2日
- 包括的な分析(複数キーワード、詳細な被リンク分析を含む):3〜5日
効率的に分析を進めるコツは以下の通りです。
テンプレートを用意しておくことで、毎回同じ作業を繰り返す必要がなくなります。一度テンプレートを作成すれば、2回目以降は大幅に時間を短縮できます。
ツールを活用することで、手作業で行っていた作業を自動化できます。特に順位チェックやキーワード抽出などは、ツールで効率化すべきです。
分析の目的を明確にし、必要な情報だけに絞ることで、無駄な時間を削減できます。完璧を目指すのではなく、80%の完成度で実行に移すことが重要です。
チーム で分担することで、一人で全てを行うよりも短時間で完了できます。例えば、キーワード調査、コンテンツ分析、被リンク分析をそれぞれ別の担当者が行うという方法です。
競合分析をしても順位が上がらないのはなぜ?
競合分析をしただけでは順位は上がりません。分析結果を基にした適切な施策の実行が必要です。
順位が上がらない主な原因は以下の通りです。
分析結果を施策に落とし込めていない場合、レポートを作成しただけで満足してしまい、実際のコンテンツ改善やリンク獲得などの施策を実行していないケースがよくあります。
差別化ができていない場合、競合と同じ内容のコンテンツを作っても、後発である自社が評価されにくいです。競合を上回る独自の価値を提供する必要があります。
技術的なSEO課題がある場合、コンテンツの質を改善しても、サイトの表示速度が遅い、モバイル対応が不十分、クロールエラーがあるなどの技術的問題があると、順位が上がりにくくなります。
ドメインパワーの差が大きすぎる場合、競合のドメインパワーが自社よりはるかに高い場合、コンテンツの質だけでは追いつけません。この場合は、より競合が弱いキーワードを狙うか、被リンク獲得に注力する必要があります。
効果が出るまでの時間が不足している場合、SEO施策の効果が現れるまでには、通常3ヶ月〜6ヶ月程度かかります。施策を実行してすぐに順位が上がるわけではないことを理解しておきましょう。
対策として、以下を実践しましょう。
- 分析結果から具体的なアクションプランを作成し、確実に実行する
- 競合を参考にしつつ、独自の価値を必ず加える
- コンテンツだけでなく、技術的SEOも並行して改善する
- 定期的に効果測定を行い、施策を調整する
- 長期的な視点で取り組む(最低3〜6ヶ月は継続)
SEO対策は株式会社アリカに相談
まとめ
SEO対策における競合分析は、検索上位を目指すために欠かせない重要なプロセスです。本記事で解説した内容を振り返りましょう。
競合分析とは、検索エンジンで上位表示されている他社サイトの戦略を調査・分析することです。これにより、上位表示に必要な要素が明確になり、自社の差別化ポイントを見つけられます。
分析を始める前には、対象キーワードの選定、競合サイトの選定、使用するツールの準備が必要です。無料ツールでも基本的な分析は十分可能ですが、より詳細な分析には有料ツールの活用も検討しましょう。
具体的な分析手順として、以下のステップを実施します。
- Google検索で上位10サイトをリストアップ
- 複数キーワードで競合を洗い出し
- 競合候補を3〜5社に絞り込み
- 5つのポイント(文字数・構成、タイトル、コンテンツの質、被リンク、更新頻度)を詳細に分析
分析で得たデータは、実際のSEO戦略に落とし込むことが重要です。競合との差別化ポイントを見つけ、コンテンツギャップ分析で勝てるキーワードを発見し、競合の弱点を突く記事企画を作成しましょう。
競合分析でよくある失敗として、以下の5つがあります。
- 競合の真似だけで終わってしまう
- データ収集に時間をかけすぎる
- 自社の強みを無視した戦略になる
- 分析結果を活用できず放置する
- 競合を間違えて選定してしまう
これらの失敗を避け、適切な競合分析を継続的に実施することで、SEO対策の効果を最大化できます。
業界や目的によって分析のポイントは異なります。EC・通販サイト、ブログ・メディアサイト、ローカルビジネス、BtoBサイトなど、それぞれの特性に応じた分析を行いましょう。
競合分析は一度行えば終わりではなく、定期的に更新することで価値を維持できます。市場は常に変化しており、競合の戦略も進化し続けるため、継続的なモニタリングが重要です。
今日から競合分析を始めて、自社のSEO戦略を強化しましょう。まずは無料ツールを使った簡易的な分析から始め、徐々に分析の精度を高めていくアプローチがおすすめです。
SEO対策は長期的な取り組みですが、適切な競合分析に基づいた戦略を実行することで、着実に成果を上げられます。本記事で紹介した方法を参考に、ぜひ実践してみてください。